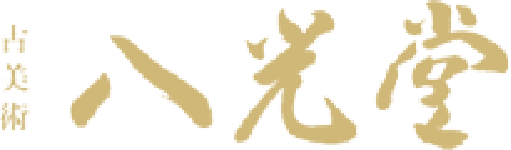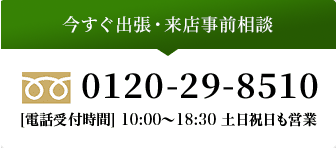【名古屋店:茶道具買取】黒田正玄 蓋置
千利休によって完成に至った「侘び茶」の文化は広い階層に愛され、茶碗に始まる茶道具や茶室を彩る装飾品、おもてなしの所作から今日の日本文化の根幹が作られたと言っても過言ではありません。
一方で、茶道に興味を持ちつつも、実際に茶席にお呼ばれすると、どのような準備をしていったらよいか戸惑ってしまいますよね。茶席は、もてなすこと・もてなされることを互いに楽しむところに良さがありますので、あまり細かなことまでは気にする必要はないのですが、慣れてきたところで小道具にもこだわってみると、茶席の場がさらに面白くなります。
さて、今回はそんな茶道具をつくる「千家十職」の識家の一人、黒田正玄(くろだしょうげん)についてお話ししたいと思います。
千家十職の中の黒田家
そもそも、「千家十職」というのは、茶道具を作る専門の職人たちの事で、中でも三千家(表千家・裏千家・武者小路千家)の茶道具を代々にわたり制作を任された職人たちの総称です。
三千家好みの茶道具を作れる職人は限られており、行事や年忌における役割もあるため、徐々に固定されていき、明治の頃に現在の十職に整理され、「千家十職」と呼ばれるようになりました。いわば、お茶道具のスペシャリスト集団ですね。かっこいいです。
その中で、黒田家は、竹細工や柄杓師を務めています。江戸時代より約四百年に渡り、茶杓、柄杓のほか、台子や香合、花入など、竹を用いた道具を千家に納めてきた家系です。黒田正玄は、黒田家の当主が代々襲名している名前なのです。

400年に渡る伝統の継承
初代正玄は、元々、武士で丹羽長重に仕えていました。しかし関ヶ原の戦いで丹羽氏は西軍に付き改易(かいえき=身分および土地家屋の没収)、浪人となったために剃髪して大津に移り住み、竹細工職人となりました。その時の師匠が、井戸守でありながら、豊臣秀吉に柄杓を納めて「天下一」と称されていた一阿彌という人物であったと言われています。
竹細工が評判を呼び、上京。評判の竹細工師となった正玄は、小堀遠州の元で茶の湯を修行し、遠州の推挙により江戸幕府御用達の柄杓師となりました。以後明治維新を迎えるまで、三千家・将軍家の御用達柄杓師となりました。
後継者問題によって、一時空席となりかけた時期もありましたが、今でもその伝統は続いています。当代は、13代の長女である益代が、14代目として家督を継ぎ、黒田家で初の女性当主となっています。
今までの技術・伝統を継承していくと同時に、代ごとに特徴があり、新しい試みを取り入れている作品など、見れば見るほど深いお茶の世界に引き込まれていきます。
竹の個性を活かす選竹眼

竹細工は、竹に凝った細工を加えるというより、竹の素材を活かす細工が求められ、竹自体の素朴な美しさと材質を活かすことに技術を駆使する必要があります。
竹細工師の仕事は、竹の色合い、太さ、節の間隔など、1本1本の個性を見極め、使う竹を選ぶことから始まります。しかし、その前段階、伐採してきた竹を素材として使えるようにするまでに、とても時間がかかるのです。
竹の中の水分が最も少ない時期の、11月ごろに竹を選定・切り出します。伐採した竹は、2か月ほど乾かし、その後、畳一畳ほどの火鉢で竹のあぶり(脂抜き)が行われ、さらに1か月半ほど天日干しし、最後に風通しのよい日陰で4~5年寝かせて、初めて茶道具の素材となるのです。この過程で虫くいやひび割れなど、使用できなくなる竹も多く、作品として使用できる竹は数パーセントということです。そうして手間と時間をかけ丁寧に下準備をした竹は光沢が増し、素材の美しさが際立ってくるのです。
茶杓などは、一見同じように見えますが、じっくりと拝見すると、削り方、色・樋の入り方、節の扱い方で、それぞれ異なる個性を表す事ができるのです。柄杓は茶会の度に新しいものを使うしきたりになっていて、流儀や家元の好みによって形の違いがあり、なんと六十六通りにも及ぶと言われています。そういった要望に応え続ける為にも、竹の個性を活かす選竹眼こそ、竹細工師に求められている技術なのです。