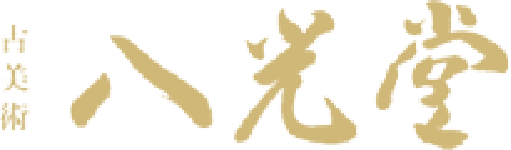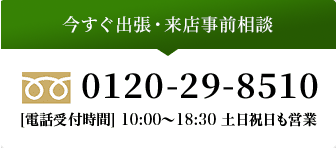20世紀のパリで活躍した愛らしさを追求した画家“マリー・ローランサン”
マリー・ローランサンについて
20世紀の西洋では、芸術とは重厚で高尚、深淵なものであるべきと言われていました。
その伝統的な芸術感に反し、可愛いものを愛する気持ちと、自身の感性をひたすらに信じながら愛らしさを追求し、たった一人で全く新しい絵画を生み出した女性画家、マリー・ローランサン。
本日は、マリー・ローランサンのあまり知られてはいないだろう波乱万丈な人生を紐解いていきたいと思います。
マリー・ローランサンは1883年10月31日にフランスのパリで生まれました。彼女の母親は、妻子ある代議士との間にマリーをもうけ、未婚のまま裁縫や刺繍の仕事をしながら一人でマリーを育てました。読書好きでラテン語も読める母親の影響からか、マリーも読書や絵を描くのが好きになり、いつしか画家になる事を夢見るようになります。
画家になる夢は見ていたものの、彼女は教師を目指し、師範学校への受験勉強をしていました。しかし、19歳で志望を変更、一転して陶器の絵付け講習やパリ市立のデッサン講習に通います。21歳でアカデミー・アンベールに通い、本格的に絵画の勉強を始めました。ここで、キュビズムの画家となるジョルジュ・ブラックと出会うのです。
その後ジョルジュ・ブラックに誘われ、余り気は進まないもののアトリエ「洗濯船」(パリのモンマルトルにあるアトリエ兼用の古いアパート)に出入りをするようになります。ここにはピカソやヴァン・ドンゲンなど貧しいが才能に溢れた天才たちが住んでおり、多くの芸術家たちのたまり場でした。その内の一人が詩人のギョーム・アポリネールでした。
マリーとアポリネールが激しい恋に落ちるのに時間はかかりませんでした。
アポリネールは毎日のように詩を書いてはマリーへ送り、彼女の画才をあちこちで宣伝してまわりました。そのうちにアポリネールは詩人として評価され始め、マリーは画家として売れ始めます。
才能豊かな二人の恋は永遠に続くかと思われましたが、鋭い感性と激しい個性はぶつかり合い、亀裂を生み始めました。そんな時に二人の破局を決定づける事件が起きるのです。1911年、アポリネールがルーヴル美術館で起きた『モナ・リザ』盗難事件の共犯容疑で逮捕されたのです。疑いは晴れましたたが、この事件でアポリネールとロ-ランサンの二人の関係はぎくしゃくしたものになり、ついに5年間の燃えるような愛は終焉を迎えます。
30歳になる頃には、淡い青、緑、紅の色調を用い、馬や鳥などを添景としながら女性の姿をとらえるという幻想的な画風を確立していきます。「エコール・ド・パリ」と呼ばれた多くの芸術家たちの中でも、有望な新進画家として世に知られる存在となったのです。
そんな中、突然最愛の母を亡くします。母の死による孤独に耐えられなかったマリーは31歳でドイツ人画家のオットー・フォン・ヴェッチェン男爵と結婚。私生児だった彼女が公爵夫人という肩書きを欲した為とも言われています。
結婚によりドイツ国籍になったマリーは、第一次世界大戦が始まると七年間に及ぶ亡命生活を余儀なくされました。亡命先のマドリード(スペイン)でマリーを待ち受けていたものは、アポリネールとは正反対のガサツで女性の心を解さない夫との地獄の日々でした。愛する故郷や親しい友人達と離れたこの間の作品は、どれも孤独で悲しさに溢れていました。
そんなマリーを慰めてくれたのはニコル・グレーでした。彼女は生涯の親友になりましたが、同時にマリーを同性愛に目覚めさせるきっかけになったのです。
ようやくフランス永住の許可を得たマリーは1921年にパリに戻ります。そして翌年39歳で夫と正式に離婚をしました。
戦後、離婚して単身パリに戻ってからの彼女の画風は大きく変化しました。それまで彼女の絵の代名詞であった『憂い』を消し去り、官能性があり華やかな夢の世界の幸せな少女像を生み出したのです。
マリーは「狂乱の1920年代」のパリで、時代の雰囲気の表現者となりました。パリの社交界ではマリーに肖像画を注文することが上流婦人の流行となったのです。
その後40歳でロシアバレエ団ディアギレフの舞台「牝鹿」の舞台装飾と衣装を担当。以降、舞台装飾の依頼を多く受け、この分野でも成功を収めます。
1956年6月8日、マリーは自宅で心臓発作により亡くなりました。享年72歳でした。彼女は遺書を残しており、埋葬の際には遺言に従って、亡骸は純白のドレスに包まれ、手には赤いバラを、胸にはアポリネールより若き日に送られた手紙の束が置かれたそうです。
マリーが人生で最後まで愛した人、それはアポリネールだったのかもしれません。